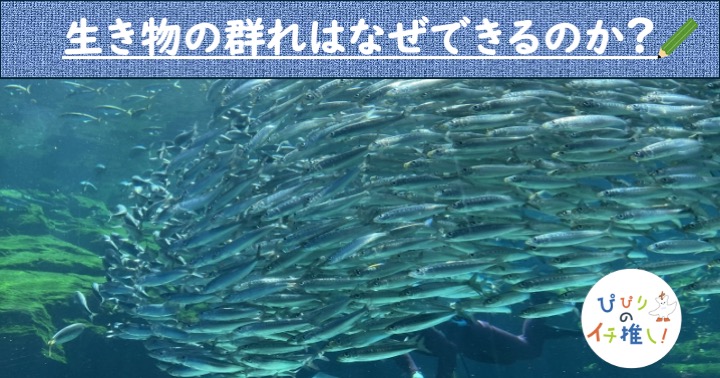2026/01/23
2026年一発目のぴぴりのイチ推し!は、アクセス数ランキングをお届けします!
本記事では、ランキング記事前編として、過去1年間(2024年12月〜2025年11月)に公開された21本の記事の中から、特にアクセス数が多かったものをランキング形式でご紹介して、昨年のぴぴりのイチ推し!記事を振り返りたいと思います。
また、ランキング記事後編では、今まで公開された全記事を対象とした2025年のアクセス数ランキングと、担当者のおすすめ記事をご紹介します。
それでは、早速ランキングで昨年のぴぴりのイチ推し!を振り返ってみましょう!
(集計期間:2024年12月1日〜2025年11月30日)
第5位 動物に心はあるか?【東大生ライターが岡ノ谷 一夫先生の講義を紹介】(「動物に心があるか」岡ノ谷一夫先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_5793/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_25_2021_friday_okanoya/
動物にも感情や時間感覚があったり、コミュニケーションをとっていたりしそうだというのは想像には易いですが、それを科学的に証明するのは簡単ではないようです。何より、生物によってその方法や特徴は様々です。タイトルの通り、動物に「心」があるのか、という問いに対し生物心理学や動物行動学などと呼ばれる学問の立場で科学的な答えを探っていくのが、こちらの講義・記事のテーマです。様々な実験の様子が紹介されており、見ているだけで実験に参加したようで面白い点も魅力の一つです。
第4位 あなたはふだん文章の「声」を読んでいますか?(阿部 公彦先生講義動画紹介)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_5801/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2021_friday_abe/
講義で紹介される「らくがき式」では、文章につっこみなどを書き込みながら本を読んでいきます。文章や言葉選びの特徴についてより深く考えられるこの手法を、記事でもご紹介しています。普段は無意識で聞いている文章の「声」が、「らくがき式」で読むと可視化され、より深く理解できるそう。現代文が苦手だった中学生時代の私に教えてあげたいものです。また、東大の祝辞を読み解くというのも、東大の講義ならではで、おすすめポイントです。
第3位 動物を殺すことは罪か?民俗学から考える(「民俗学から考える動物の恵みと供養」菅豊先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_4537/ コラムはこちらから:http://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2014_koukaikouza_suga/
2025年は、「今年の漢字」が「熊」に選ばれたように、各地でクマの出没が話題となり、同時にクマの駆除も重要なトピックとなりました。害虫や鳥獣駆除のため、時には動物の命を奪ってしまうこともあります。また、食べるために動物を殺めるのも、避けられない行為と言えるかもしれません。そんな「動物を殺すこと」そして「動物を供養すること」について、民俗学の観点から考えるのが、この講義・記事のテーマです。特に2025年だからこそ、多くの人が改めて考えるきっかけになったのではないでしょうか。
第2位 光合成人間をつくる!ー研究とその応用における倫理(「植物と動物の融合から生じる研究と倫理の境界」松永幸大先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_6028/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2022_koukaikouza_matsunaga/
光合成をするのは植物の特徴と言えますが、光合成をできる動物を創り出すという研究があることを、皆さんはご存じでしたか?動物が光合成をすれば、二酸化炭素を吸収して、太陽光からエネルギーを自給することもでき、環境問題の解決にもつながる可能性があるなど、夢のある話です。しかし、新たな生物を人工的に創り出すというのは、倫理的な面では様々な議論があります。光合成人間という非常にインパクトのある研究と、その周辺に存在する様々な問題について議論する講義を紹介したこちらの記事が、昨年のアクセス数第2位となりました。
第1位 環境で性別が変わる?性別の境界線を超える魚たちの世界(「オスとメスの境界を越える魚たち」大久保範聡先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_6084/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2020_koukaikouza_ookubo/
タイトルの通り、性転換をしたり、そもそも性別をもたないといった魚たちについて紹介したこちらの講義・記事。成長の過程で勝手に性別が変わるというのはなかなか特殊に思えますが、1種類や2種類の魚に限った話ではありません。実は、皆さんの身近な魚もそうなのかも。どのようにして性別が変わるのか、そもそもなぜ性別が変わるのか。たくさんの魚たちの写真とともに学ぶことができ、まるで水族館に行った気分になれます(というか行きたくなります)。生き物の不思議に迫る、老若男女問わず楽しめる記事が第1位となりました。
2026年もぴぴりのイチ推し!をよろしくお願いいたします
ぴぴりのイチ推し!では、引き続き、東大TVで公開している、東京大学の講義・講演をご紹介し、東大で行われている研究や学問の魅力を多くの人に知ってもらうための記事を公開していきます。ぜひ、2026年もお楽しみください!
そして、UTokyo OCWの講義動画をご紹介している「だいふくちゃん通信」でもランキング記事をお届けしています。ぜひこちらもお楽しみください。
後編もお楽しみに!
【2025年ランキング記事はこちら】【だいふくちゃん通信】2025年アクセス数ランキング!【ぴぴりのイチ推し!】2025年アクセス数ランキング!(この記事)【だいふくちゃん通信】2025年アクセス数総合ランキング&おすすめ3選!(1月30日頃公開予定)【ぴぴりのイチ推し!】2025年アクセス数総合ランキング&おすすめ3選!(2月上旬公開予定)
【過去のランキング記事はこちら】2024年だいふくちゃん通信アクセス数ランキング2024年ぴぴりのイチ推しアクセス数ランキング2023年だいふくちゃん通信アクセス数ランキング2022年だいふくちゃん通信アクセス数ランキング
<文/おおさわ(東京大学学生サポーター)>
●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。
本記事では、ランキング記事前編として、過去1年間(2024年12月〜2025年11月)に公開された21本の記事の中から、特にアクセス数が多かったものをランキング形式でご紹介して、昨年のぴぴりのイチ推し!記事を振り返りたいと思います。
また、ランキング記事後編では、今まで公開された全記事を対象とした2025年のアクセス数ランキングと、担当者のおすすめ記事をご紹介します。
それでは、早速ランキングで昨年のぴぴりのイチ推し!を振り返ってみましょう!
(集計期間:2024年12月1日〜2025年11月30日)
第5位 動物に心はあるか?【東大生ライターが岡ノ谷 一夫先生の講義を紹介】(「動物に心があるか」岡ノ谷一夫先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_5793/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_25_2021_friday_okanoya/
動物にも感情や時間感覚があったり、コミュニケーションをとっていたりしそうだというのは想像には易いですが、それを科学的に証明するのは簡単ではないようです。何より、生物によってその方法や特徴は様々です。タイトルの通り、動物に「心」があるのか、という問いに対し生物心理学や動物行動学などと呼ばれる学問の立場で科学的な答えを探っていくのが、こちらの講義・記事のテーマです。様々な実験の様子が紹介されており、見ているだけで実験に参加したようで面白い点も魅力の一つです。
第4位 あなたはふだん文章の「声」を読んでいますか?(阿部 公彦先生講義動画紹介)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_5801/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2021_friday_abe/
講義で紹介される「らくがき式」では、文章につっこみなどを書き込みながら本を読んでいきます。文章や言葉選びの特徴についてより深く考えられるこの手法を、記事でもご紹介しています。普段は無意識で聞いている文章の「声」が、「らくがき式」で読むと可視化され、より深く理解できるそう。現代文が苦手だった中学生時代の私に教えてあげたいものです。また、東大の祝辞を読み解くというのも、東大の講義ならではで、おすすめポイントです。
第3位 動物を殺すことは罪か?民俗学から考える(「民俗学から考える動物の恵みと供養」菅豊先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_4537/ コラムはこちらから:http://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2014_koukaikouza_suga/
2025年は、「今年の漢字」が「熊」に選ばれたように、各地でクマの出没が話題となり、同時にクマの駆除も重要なトピックとなりました。害虫や鳥獣駆除のため、時には動物の命を奪ってしまうこともあります。また、食べるために動物を殺めるのも、避けられない行為と言えるかもしれません。そんな「動物を殺すこと」そして「動物を供養すること」について、民俗学の観点から考えるのが、この講義・記事のテーマです。特に2025年だからこそ、多くの人が改めて考えるきっかけになったのではないでしょうか。
第2位 光合成人間をつくる!ー研究とその応用における倫理(「植物と動物の融合から生じる研究と倫理の境界」松永幸大先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_6028/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2022_koukaikouza_matsunaga/
光合成をするのは植物の特徴と言えますが、光合成をできる動物を創り出すという研究があることを、皆さんはご存じでしたか?動物が光合成をすれば、二酸化炭素を吸収して、太陽光からエネルギーを自給することもでき、環境問題の解決にもつながる可能性があるなど、夢のある話です。しかし、新たな生物を人工的に創り出すというのは、倫理的な面では様々な議論があります。光合成人間という非常にインパクトのある研究と、その周辺に存在する様々な問題について議論する講義を紹介したこちらの記事が、昨年のアクセス数第2位となりました。
第1位 環境で性別が変わる?性別の境界線を超える魚たちの世界(「オスとメスの境界を越える魚たち」大久保範聡先生)
講義動画はこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/lecture_6084/ コラムはこちらから:https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili25_2020_koukaikouza_ookubo/
タイトルの通り、性転換をしたり、そもそも性別をもたないといった魚たちについて紹介したこちらの講義・記事。成長の過程で勝手に性別が変わるというのはなかなか特殊に思えますが、1種類や2種類の魚に限った話ではありません。実は、皆さんの身近な魚もそうなのかも。どのようにして性別が変わるのか、そもそもなぜ性別が変わるのか。たくさんの魚たちの写真とともに学ぶことができ、まるで水族館に行った気分になれます(というか行きたくなります)。生き物の不思議に迫る、老若男女問わず楽しめる記事が第1位となりました。
2026年もぴぴりのイチ推し!をよろしくお願いいたします
ぴぴりのイチ推し!では、引き続き、東大TVで公開している、東京大学の講義・講演をご紹介し、東大で行われている研究や学問の魅力を多くの人に知ってもらうための記事を公開していきます。ぜひ、2026年もお楽しみください!
そして、UTokyo OCWの講義動画をご紹介している「だいふくちゃん通信」でもランキング記事をお届けしています。ぜひこちらもお楽しみください。
後編もお楽しみに!
【2025年ランキング記事はこちら】【だいふくちゃん通信】2025年アクセス数ランキング!【ぴぴりのイチ推し!】2025年アクセス数ランキング!(この記事)【だいふくちゃん通信】2025年アクセス数総合ランキング&おすすめ3選!(1月30日頃公開予定)【ぴぴりのイチ推し!】2025年アクセス数総合ランキング&おすすめ3選!(2月上旬公開予定)
【過去のランキング記事はこちら】2024年だいふくちゃん通信アクセス数ランキング2024年ぴぴりのイチ推しアクセス数ランキング2023年だいふくちゃん通信アクセス数ランキング2022年だいふくちゃん通信アクセス数ランキング
<文/おおさわ(東京大学学生サポーター)>
●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。